臨床顧問の第三者視点による
定期的な同時臨床介入
自費リハビリの効果を最大限に
効果的な介入を行うためには、2つの事が大事であると考えています。
それは、
が必要であると考えます。
【批判的吟味によるセラピストの内省】
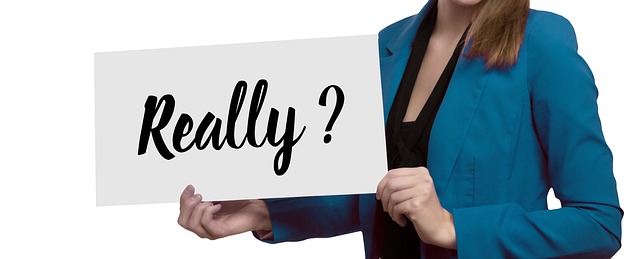
セラピストは利用者に介入する際に「評価と介入を同時進行」でしていかなければなりません。
よくあるのは、「エビデンスでは、これが推奨されているから~」や「著名な〇〇先生がこう言っていたから~」という臨床推論を行わない短絡的なセラピストが一定います。
しかし、エビデンスも確実にセラピストは知っておく必要がありますが、個々人によって性格が違うように非常に幅が広い個別性があります。
その個別性を踏まえ、目標設定に対しての問題点を徹底的にあぶり出していきます。
その問題点に対して、「硬いからとりあえず緩める」ということはしません。
【姿勢を変換する事でその状態はどのように変わるのか?】など様々な事を検証して仮説を立てます。
例えば、
・座っている姿勢では、麻痺した手は伸びているが、立ってしまうと手が曲がってしまう。
・五十肩の人で仰向けや座っている時は手が上がるが、立ってしまうと手があげずらい。
などなど沢山の【謎】が生まれます。
その【謎】を解いていく過程が仮説検証作業と言います。
First Stepはその【仮説検証作業)】を徹底的にこだわり、その問題点に介入する際に
「どの姿勢で介入するのか」 「どのように操作するのか」 「刺激の加え方、強さ、速さはどうするのか」「操作をする際にセラピストの各指はどのような役割を持たせているのか」
あげればキリがありませんが、結果を出すということに強いこだわりを持っています。
【第三者視点による評価】

人間だれしも自分が出した考え方に否定的な見方をあまりしません。
なぜなら、自分の知っている知識の中でしか推論できないからです。
そのため、多くの人が勉強をし、自己研鑽に励むと思います。
しかし、自己研鑽で勉強するのは至極当然の事ではありますが、勉強をしている人のリテラシーによっても勉強の内容は変化してしまいます。
例えば、
「脳卒中片麻痺患者の歩行時における膝過伸展は下腿三頭筋の痙縮が原因である」
と巷では有名な話です。
確かにそうであると考えられますが、「振り出しの時に足の内反が出る」というのは「下腿三頭筋の痙縮」が原因と短絡的にいう事ができません。
「麻痺した側を振り出す時に内反がでるのは、麻痺してない側の支えがしっかりしていないから??」
と考えることもできます。
一概には仮説検証作業をしてみないとわかりませんが、
「人によって原因が違う」という事です。
ここで先ほどの「自分の知っている知識の中でしか推論しない」という所が問題になります。
そのため、First Stepでは、より臨床経験が豊富で結果を出す事に重点を置いている、臨床顧問と定期的に同時介入を行いながら批判的吟味をしています。